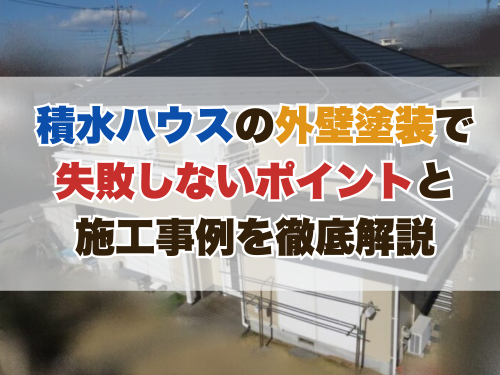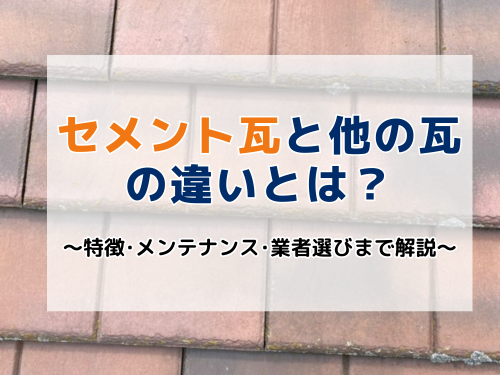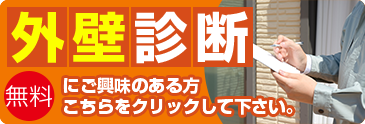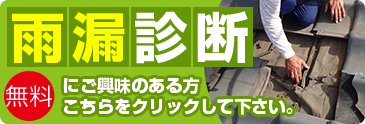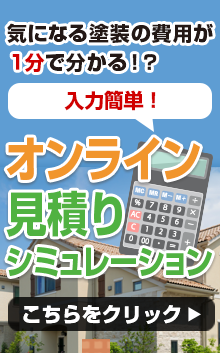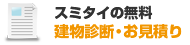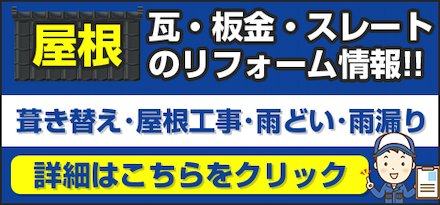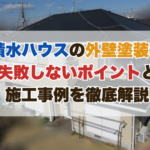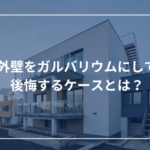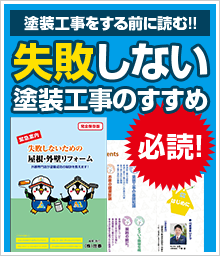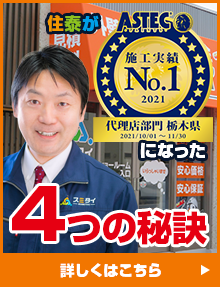瓦屋根に塗装は必要?費用相場・塗料の選び方・施工手順を徹底解説!
2025.10.23 (Thu) 更新

屋根の瓦に塗装が必要だと聞いたけれど、「本当に塗るべきなの?」「費用はどれくらい?」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。実は、瓦の種類によっては塗装が必要なものとそうでないものがあり、判断を間違えると不要な出費や施工トラブルにつながることもあります。
本記事では、瓦屋根の塗装が必要なケースや向き不向きの見分け方、塗装にかかる費用相場、施工の流れ、業者選びのポイントまで、屋根リフォームを検討する方にとって役立つ情報をわかりやすく解説していきます。屋根を長持ちさせ、美観を保つために、まずは正しい知識を身につけましょう。
目次
- 1.瓦屋根に塗装は必要?まずは基礎知識から
- 1-1 塗装が不要な瓦:粘土瓦(日本瓦・いぶし瓦・陶器瓦など)
- 1-2 塗装が必要な瓦:セメント瓦・モニエル瓦・金属瓦
- モニエル瓦(乾式コンクリート瓦)
- 金属瓦(ガルバリウム鋼板など)
- 1-3 瓦の素材によって、塗装の要・不要が明確に分かれる
- 2.瓦屋根の塗装にかかる費用相場
- 2-1 全体費用の目安(30〜40坪の住宅の場合)
- 2-2 平米単価ベースで見る費用相場
- 2-3 工程ごとの費用内訳(例:屋根面積80㎡の場合)
- 2-4 費用が高くなる要因とその理由と抑えるためにできること
- 3.塗装すべき劣化サインと時期の目安
- 3-1色褪せ・ツヤの消失は初期サイン
- 3-2 コケ・藻・カビの発生
- 3-3 瓦のひび割れ・欠け・浮き
- 3-4 漆喰の崩れ・棟瓦の劣化
- 3-5 金属部分のサビ・釘の浮き
- 3-6 雨漏り・屋根裏の湿気
- 3-7 築年数を目安にするのもひとつの方法
- 3-8 劣化サインを見つけたらどうする?
- 4.瓦屋根塗装のメリットとデメリット
- 4-1 瓦屋根塗装のメリット
- 4-2 瓦屋根塗装のデメリット・注意点
- 4-3 塗装の目的と屋根の状態を見極めよう
- 5.塗装の流れと工期の目安
- 5-1 ステップ1:事前調査・現地確認・プラン提案
- 5-2 ステップ2:足場設置・養生作業
- 5-3 ステップ3:高圧洗浄
- 5-4 ステップ4:下地補修・処理作業
- 5-5 ステップ5:下塗り(プライマー)
- 5-6 ステップ6:中塗り・上塗り
- 5-7 ステップ7:完了検査・タッチアップ・足場解体
- 5-8 ステップ8:保証書の発行・アフターサポート
- 5-9 工期の目安(天候にもよる)
- 6.塗料の選び方とおすすめの種類
- 6-1 塗料選びの基本的な考え方
- 6-2 主な塗料の種類と特徴(瓦屋根対応)
- 6-3 瓦屋根におすすめの塗料
- 7.DIYと業者依頼、どちらがいい?
- 7-1 DIYをおすすめしない理由
- 7-2 業者に依頼するメリット
- 8.瓦屋根の塗装に関するよくある質問(Q&A)
- 8-1 Q1. すべての瓦に塗装は必要ですか?
- 8-2 Q2. 屋根塗装のタイミングはいつが最適?
- 8-3 Q3. 雨漏りしてから塗装すればいいですか?
- 8-4 Q4. 火災保険や助成金は使えますか?
- 8-5 Q5. 業者選びで気をつけるべき点は?
- 9.まとめ
1.瓦屋根に塗装は必要?まずは基礎知識から
屋根塗装というと、外観の美しさを保つための「見た目のリフォーム」と思われがちですが、実際には建物を雨風や紫外線から守る「防水・防腐・劣化防止」のための重要なメンテナンスです。特に瓦屋根の場合は、瓦の素材によって“塗装が必要なケース”と“塗装してはいけないケース”があるため、まずはその違いを正しく理解することが大切です。
1-1 塗装が不要な瓦:粘土瓦(日本瓦・いぶし瓦・陶器瓦など)

日本家屋や和風建築によく使われているのが「粘土瓦(焼き瓦)」です。これは粘土を高温で焼き固めた瓦で、以下のような特徴があります。
1-2 塗装が必要な瓦:セメント瓦・モニエル瓦・金属瓦

一方、セメントやコンクリートで作られた瓦は、塗装による保護が不可欠です。
セメント瓦(コンクリート瓦)
- 主原料はセメントで、製造時に工場で塗装が施されていますが、この塗膜は10~15年程度で劣化します。
- 塗膜が劣化すると、瓦自体が水を吸い込みやすくなり、ひび割れ・変色・凍害による破損の原因に。
- 定期的に再塗装することで、防水性・耐久性・美観を回復できます。
モニエル瓦(乾式コンクリート瓦)

- セメント瓦の一種で、表面に「スラリー層」と呼ばれる着色層があり、通常の塗装手順では塗料が定着しにくい点が特徴です。
- スラリー層を高圧洗浄やケレン作業でしっかり除去してから、専用の下塗り材(スラリー強化プライマーなど)を使用する必要があります。
- モニエル瓦は見た目が陶器瓦に似ているため、誤って“塗装不要”と判断されやすく、注意が必要です。
金属瓦(ガルバリウム鋼板など)

- 金属製の屋根材は錆に弱いため、塗装での防錆処理が必要です。
- 使用環境にもよりますが、15~20年ごとの再塗装が推奨されます。
- 最近のガルバリウム製は耐久性が高められていますが、それでも経年で色褪せや防水性低下が起こります。
1-3 瓦の素材によって、塗装の要・不要が明確に分かれる
| 瓦の種類 | 塗装の必要性 | 耐用年数 | メンテナスの内容 |
| 日本瓦・陶器瓦・いぶし瓦 | 不要 | 50〜100年 | 漆喰や棟の補修が中心 |
| セメント瓦 | 必要(10〜15年ごと) | 約30〜40年 | 定期的な塗装で耐久性維持 |
| モニエル瓦 | 必要(要スラリー層処理) | 約30〜40年 | 特殊な下処理と塗装が必須 |
| 金属瓦 | 必要(15〜20年ごと) | 約30年 | 防錆・塗装メンテが必要 |
自宅の屋根がどの瓦に分類されるのかは、見た目だけでは判断が難しいこともあります。まずは屋根専門の業者に無料点検を依頼し、瓦の種類と状態を正確に把握することが、塗装の必要性を見極める第一歩です。
2.瓦屋根の塗装にかかる費用相場
瓦屋根の塗装を検討する際、多くの方が最も気になるのが「一体いくらかかるのか?」という点です。しかし、費用は一律ではなく、屋根の面積・形状・素材・劣化の度合い・使用塗料の種類など、さまざまな要素によって変動します。ここでは、一般的な相場感と、費用に影響する要素について詳しく見ていきましょう。

2-1 全体費用の目安(30〜40坪の住宅の場合)
一般的な戸建住宅(延床30〜40坪程度)で、セメント瓦やモニエル瓦の屋根塗装を行う場合の費用相場は、60〜100万円前後が目安です。これは屋根面積でいうと約60〜100㎡程度の規模で計算されています。
以下は、塗料グレード別の大まかな総額イメージです。
| 塗料の種類 | 総額目安(60㎡) | 総額目安(100㎡) |
| ウレタン系 | 約40〜60万円 | 約60〜80万円 |
| シリコン系 | 約50〜70万円 | 約70〜90万円 |
| フッ素系 | 約60〜90万円 | 約80〜110万円 |
| 無機塗料 | 約70〜100万円 | 約90〜130万円 |
※上記は足場・高圧洗浄・下地処理・下塗り〜上塗りの工程をすべて含んだ概算です。
2-2 平米単価ベースで見る費用相場
屋根塗装は基本的に㎡単価で費用が算出されます。塗料の種類により価格帯は以下の通りです。
| 塗料の種類 | 単価(㎡あたり) | 特徴・耐用年数 |
| ウレタン塗料 | 1,800〜2,800円 | 比較的安価だが耐久性はやや低め(5〜8年) |
| シリコン塗料 | 2,000〜3,000円 | コストと耐久性のバランスが良く人気(8〜12年) |
| フッ素塗料 | 3,000〜4,800円 | 高耐候・長寿命・高価格(12〜15年) |
| 無機塗料 | 4,500〜5,500円 | 超高耐久・最上級グレード(15年以上 |
㎡単価に加えて、足場代や諸経費(養生・廃材処理など)が発生しますので、単価×面積だけでなく、総額のバランスで判断することが大切です。
2-3 工程ごとの費用内訳(例:屋根面積80㎡の場合)
| 工程内容 | 費用目安 | 備考 |
| 足場設置 | 15〜25万円 | 屋根の高さ・形状で変動あり |
| 高圧洗浄 | 1〜3万円(㎡単価200〜400円) | 苔・汚れ・旧塗膜を除去する重要工程 |
| 下地処理 | 5〜10万円程度 | クラック補修・ケレン作業など |
| 下塗り〜上塗り | 15〜40万円程度 | 塗料の種類・塗布回数で大きく変動 |
| その他諸経費 | 5〜10万円 | 養生・運搬・廃材処理など |
| 合計 | 約60〜90万円 | 一般的な戸建住宅の相場感 |
特に下地処理と塗料の選定によって金額差が出やすく、劣化が進んでいる場合やモニエル瓦など特殊な瓦を使っている場合は、費用が高くなる傾向があります。
2-4 費用が高くなる要因とその理由と抑えるためにできること
以下の条件に該当すると、相場より費用が高くなることがあります。
【費用が高くなる要因とその理由】
- 屋根の劣化が進んでいる
クラック補修や棟部の補修など下地処理が増える
- 屋根の形状が複雑(切妻・入母屋・急勾配など)
作業の安全性確保に時間と手間がかかる
- モニエル瓦や古いセメント瓦を使用している
スラリー層の除去や専用下塗り材の追加が必要
- 足場を再利用できない/設置に制限がある
高所や狭小地など、設置コストが増加
- 高耐久塗料を選択した
長寿命=単価アップ。ただし、長期的に見れば経済的
【費用を抑えるためにできること】
- 複数社での相見積もりを必ず実施する
単価・工法・塗料・工程内容の違いを比較することで、最適な業者を選べます。
- 劣化が軽いうちに施工する
早めの塗装で下地補修の費用を抑えられます。
- 適切な塗料選びでメンテナンス周期を延ばす
高耐久のフッ素や無機塗料を選ぶことで、再塗装の頻度を減らし、長期的に費用を軽減できます。
瓦屋根塗装の費用は、一般的に60〜100万円前後が相場ですが、実際には素材・面積・塗料・施工条件によって大きく変わります。費用を正しく見積もるためには、屋根の現状をしっかり調査した上で、信頼できる業者に相談することが重要です。
費用の安さだけでなく、「耐久性」「保証」「施工実績」などもあわせて比較し、長い目で見て後悔のない屋根リフォームを行いましょう。
3.塗装すべき劣化サインと時期の目安
屋根の塗装は、見た目を整えるだけではなく、建物全体の寿命を左右する非常に重要なメンテナンスです。しかし、いつ塗装すべきかの判断は難しく、タイミングを逃すと雨漏りや下地の腐食など、より大きなトラブルを招くおそれもあります。
この章では、瓦屋根において「そろそろ塗装が必要かもしれない」と気づくためのチェックポイントと、施工を検討すべき時期の目安について詳しく解説します。

3-1色褪せ・ツヤの消失は初期サイン
紫外線や雨風に長期間さらされることで、瓦表面の塗膜は徐々に劣化していきます。特にセメント瓦やモニエル瓦は、表面の塗装が瓦本体を守る役割を果たしているため、色褪せやツヤの消失は「防水性の低下」を示すサインです。
放置してもすぐに雨漏りが起こるわけではありませんが、劣化が進行する前に塗装で塗膜を補強することで、長期的に屋根を保護できます。
3-2 コケ・藻・カビの発生
瓦に緑色や黒っぽい汚れが目立ってきたら、それはコケ・藻・カビの可能性があります。これらは、塗膜の防水性が失われ、瓦が水分を含んでいる状態を示しています。
特に北側や日当たりの悪い面に多く見られ、放置すると瓦の吸水が進み、凍害やひび割れの原因になることも。高圧洗浄や塗装の検討時期です。
3-3 瓦のひび割れ・欠け・浮き
セメント系の瓦は、経年とともに収縮と膨張を繰り返し、細かなクラック(ひび割れ)が発生しやすくなります。軽度なひびであれば補修+塗装で対応できますが、深い亀裂や欠けがある場合は、交換や葺き替えの必要が出てくることもあります。
また、瓦の一部が浮いているように見えたら、台風や地震などの外力によってズレが生じている可能性もあるため注意が必要です。
3-4 漆喰の崩れ・棟瓦の劣化

粘土瓦に多い現象ですが、棟部分に使われている漆喰が剥がれていたり、崩れていたりする場合もメンテナンスのサインです。漆喰が崩れると、瓦が固定されている力が弱まり、ズレや落下、雨漏りのリスクが高まります。
塗装だけでなく、棟部や接合部の補修・補強が必要となるケースもあります。
3-5 金属部分のサビ・釘の浮き
瓦屋根でも、谷樋(たにとい)や棟板金、雪止めなど金属部材が使用されていることがあり、これらにサビが見られる場合は要注意です。
特にサビが進行して穴が空くと、雨水が内部に侵入し、野地板や防水紙まで腐食させる恐れがあります。また、釘が浮いていたり、板金が浮いている場合も、風で飛ばされる前に補修が必要です。
3-6 雨漏り・屋根裏の湿気
劣化がかなり進んでいると、室内に雨染みが出たり、天井からポタポタと水が垂れてきたりといった明確な雨漏り症状が出ます。この段階まで放置してしまうと、塗装だけでは済まず、大がかりな補修や屋根材の交換が必要になる可能性も高まります。
早期発見のために、屋根裏(天井裏)に湿気やカビの臭いがないかをチェックしておくのも有効です。
3-7 築年数を目安にするのもひとつの方法
瓦の種類にもよりますが、一般的なセメント瓦やモニエル瓦の場合、築10〜15年程度で最初の再塗装を検討し始めるのが理想的です。その後も10〜15年ごとに定期的な塗り替えを行うことで、美観と機能性を維持できます。
なお、塗料の種類によっても耐用年数が異なるため、前回の塗装時に使用された塗料の種類を把握しておくと、次回の目安がより明確になります。
3-8 劣化サインを見つけたらどうする?
屋根は高所にあり、一般の方が安全にチェックすることは難しいものです。色褪せや苔の発生など軽微なものであっても、「気づいた時が行動のタイミング」です。以下のようなステップで対応を進めましょう。
- 地上から見える範囲をチェック
- 気になる点があれば専門業者に点検を依頼
- 写真付きの報告書をもとに、補修または塗装の提案を受ける
- 相見積もりをとって比較検討する
最近では無料点検を行ってくれる業者も多く、ドローンや屋根カメラで安全かつ正確な診断が可能になっています。信頼できる業者を選び、適切な時期に塗装・補修を行うことが、住まいを長持ちさせる秘訣です。
屋根の劣化は目に見えにくいため、気づいたときには内部まで進行していることも少なくありません。色褪せやコケといった初期症状の段階で適切に塗装を行えば、大規模な補修を避けることができます。
定期点検と早めのメンテナンスが、住まいを守る最大の防御策です。
4.瓦屋根塗装のメリットとデメリット
瓦屋根の塗装には、家の寿命や快適性に関わる多くの利点がありますが、一方で注意しなければならない点や誤った判断をすると費用や手間が無駄になってしまうリスクも存在します。ここでは、塗装を行うことの具体的なメリットとデメリットの両面から、屋根塗装の本質的な意味を解説します。
4-1 瓦屋根塗装のメリット
- 屋根材の劣化を抑え、長持ちさせる
瓦の中でもセメント瓦やモニエル瓦は、塗膜が外的ダメージから屋根材そのものを守るバリアの役割を果たしています。
塗膜がしっかり機能していれば、瓦が水を吸収するのを防ぎ、ひび割れや凍害による劣化、苔や藻の繁殖などを抑制できます。
適切な時期に塗装を行えば、瓦そのものの寿命を延ばし、30年以上使い続けることも可能です。屋根のリフォームや葺き替えに比べれば、塗装はコストも施工期間も少なく済む「延命策」として非常に有効です。
- 雨漏りのリスクを軽減できる
塗膜の防水性が失われると、瓦の隙間や下地材に水分が浸入し、やがて雨漏りへとつながります。塗装によって屋根全体を均一に保護することで、雨漏りの発生を未然に防ぐことができます。
特にモニエル瓦や古いセメント瓦は、水を吸いやすい特性があるため、防水塗装の有無で家の耐久性に大きな差が生まれます。
- 外観が一新され、建物の印象が大きく変わる
瓦屋根の塗装は、家全体の印象を大きく左右するポイントです。築年数の経過とともに色あせた屋根も、再塗装によってまるで新築のような見た目に生まれ変わります。
また、外壁や周囲の景観に合わせたカラーチェンジも可能なため、外装のトータルコーディネートにこだわりたい方にもおすすめです。
- 遮熱・断熱などの機能性を付加できる
最近の屋根塗料には、遮熱性や断熱性、防汚性などの高機能を備えたものが多数登場しています。
たとえば遮熱塗料を使えば、太陽光を効率よく反射し、屋根材の蓄熱を抑えることが可能です。これにより夏場の室内温度上昇を防ぎ、エアコン代の節約や熱中症対策にも貢献します。
高機能塗料は価格が高めですが、長期的には省エネ性や快適性を高める「投資」ともいえるでしょう。
- コケ・カビ・藻の繁殖を防げる
瓦屋根は湿気や水分がこもりやすく、放っておくとコケや藻、カビが繁殖しやすくなります。これらは美観を損なうだけでなく、瓦自体の劣化や健康リスク(カビによるアレルギーなど)にもつながります。
塗料には防カビ・防藻機能を持つものもあり、定期的な塗装によって清潔で美しい屋根を保ちやすくなります。
4-2 瓦屋根塗装のデメリット・注意点
- 費用が高額になる場合がある
瓦屋根は凹凸が多く、面積が広いため、塗装にかかる手間や材料費がスレート屋根などに比べて多くなる傾向があります。また、モニエル瓦など特殊な瓦には専用の下塗り材や洗浄作業が必要であり、工数が増えるため、結果的に費用が高額になることも。
塗料の種類によっても価格が大きく異なり、グレードの高い塗料を使えばその分費用も上乗せされます。相場は60〜100万円ほどですが、条件によってはさらに高くなることも想定されます。
- 塗装が不要な瓦もある
すべての瓦が塗装に向いているわけではありません。たとえば、日本瓦や陶器瓦、いぶし瓦などの粘土瓦は、高温で焼き固められており、もともと防水性が高く、塗装の必要がありません。
むしろ塗装してしまうと、塗膜が密着せず剥がれやすくなり、見た目の悪化や雨漏りの原因になることもあります。屋根材の種類に適したメンテナンスができるかどうかが重要です。
- 塗装の効果には限界がある
塗装はあくまで「瓦の表面を保護する手段」であり、屋根の構造自体が劣化している場合には十分な効果を得られないこともあります。
たとえば、瓦が大きく割れている、下地材が腐っている、防水シートが破れているといった状態では、塗装では対処しきれず、葺き替えや補修工事が必要になる場合があります。
- 塗装の品質は業者によって差がある
屋根塗装は専門的な技術が求められる作業です。高圧洗浄や下地処理、縁切り作業、塗料の選定、適切な乾燥時間の確保など、どの工程も適当に済ませると、数年で塗膜が剥がれるなどのトラブルにつながります。
悪質な業者では、工程を省略したり、安価な塗料を使ったりする例も報告されています。実績豊富で信頼できる業者を選ぶことが、満足のいく仕上がりに直結します。
4-3 塗装の目的と屋根の状態を見極めよう
メリット・デメリットの比較表
| 項目 | メリット | デメリット |
| 耐久性 | 塗膜で保護し、瓦の寿命を延ばせる | 塗装では補えない損傷もある |
| 防水性 | 雨漏りのリスクを軽減できる | 不適切な塗装で逆に雨漏りリスクも |
| 美観 | 色あせた屋根を一新できる | 剥がれ・色ムラが出る可能性も |
| コスト面 | 葺き替えより安価な選択肢 | 内容次第では高額になるケースも |
| 快適性 | 遮熱塗料で室内環境も改善 | 効果の体感には個人差がある |
瓦屋根の塗装は、費用も時間もかかる大きなリフォームですが、それに見合うだけの効果が得られるケースが多くあります。ただし、「すべての瓦に塗装が適しているわけではない」「屋根の状態次第では塗装より葺き替えが必要」という点を忘れてはいけません。
後悔しないためには、自宅の屋根材を正しく把握し、信頼できる業者に相談して、適切なメンテナンス方法を選ぶことが大切です。
5.塗装の流れと工期の目安
瓦屋根の塗装は、「高所作業」「専門知識」「気象条件の影響」といった要素が絡むため、計画的に進める必要があります。ここでは、一般的な屋根塗装工事の流れを8つの工程に分けて、それぞれの内容やポイント、必要日数の目安を詳しく解説します。
5-1 ステップ1:事前調査・現地確認・プラン提案
工事前には、屋根の状態を正確に把握するための「現地調査」が行われます。

調査項目の例
- 瓦の種類(粘土瓦かセメント瓦かなど)
- ひび割れや欠けの有無
- 苔・藻・カビの発生状況
- 棟瓦や漆喰の崩れ・ズレ
- 雨漏りの兆候があるか
調査方法
- はしごでの目視点検
- ドローンや高所カメラでの撮影
- 屋根裏点検(必要に応じて)
調査結果をもとに、補修の有無や塗料の種類、施工方法を提案され、正式な見積もりが出されます。ここで相見積もりを取り、納得のいく内容かを見極めることが大切です。
5-2 ステップ2:足場設置・養生作業

安全に作業を行うため、まずは足場を設置します。
- 足場組み立て時間:半日〜1日程度
- 養生の目的:
- 塗料の飛散を防止する(隣家・車・植栽などへの被害回避)
- 瓦の飛散防止や作業員の転落防止
- 使用するもの:
- メッシュシート、ブルーシート、ビニール養生材など
養生作業が丁寧であるかどうかは、その後の仕上がりや信頼度にも関わる重要ポイントです。
5-3 ステップ3:高圧洗浄

塗装前に、屋根表面の汚れや苔・カビ・古い塗膜などを高圧洗浄でしっかり除去します。
- 作業時間:半日〜1日程度(屋根面積により変動)
- 水圧:10〜15MPa程度の業務用高圧洗浄機を使用
- 注意点:
- 洗浄後はしっかり乾燥させる必要があり、1〜2日ほど空けるのが理想
- モニエル瓦などはスラリー層(表面着色層)を丁寧に削ぎ落とす必要がある
この洗浄作業が甘いと、塗料の密着性が悪くなり、数年で剥がれる原因になります。
5-4 ステップ4:下地補修・処理作業

屋根材や下地の劣化状態によっては、塗装前に補修が必要です。
- 補修の例:
- ひび割れの補修(シーリング材や専用パテ)
- 瓦のズレ直し・差し替え
- 漆喰の塗り直し
- 棟板金の釘打ち直しや錆落とし
- ケレン作業(鉄部や旧塗膜の剥離)
この作業を省略すると、いくら塗装しても劣化が再発しやすくなります。見積もり時に「補修費用」が含まれているかもチェックしましょう。
5-5 ステップ5:下塗り(プライマー)
塗装の第一層として、下塗り材(プライマーやシーラー)を塗布します。

- 目的:
- 屋根材の吸い込みを抑える
- 上塗塗料の密着性を高める
- 使用材料:
- 瓦専用プライマー
- モニエル瓦専用のスラリー強化プライマー(通常の下塗りでは不可)
- 乾燥時間の目安:2〜4時間以上(気温・湿度により変動)
下塗りをしっかり行うことで、上塗りの発色や持ちが良くなります。
5-6 ステップ6:中塗り・上塗り
屋根の本塗装工程です。一般的には中塗り→乾燥→上塗りの2回塗りで行われます。

- 中塗り・上塗りの役割:
- 中塗り:塗膜の厚みを確保し、仕上がりのベースを作る
- 上塗り:耐候性・防水性・美観を仕上げる最終工程
- 使用塗料:ウレタン・シリコン・フッ素・無機など(事前のプランで選定)
- 乾燥時間:工程ごとに最低2〜4時間、理想は1日空ける
※天候や湿度によって乾きにくくなるため、雨の日や強風の日は作業を中断します。
5-7 ステップ7:完了検査・タッチアップ・足場解体
塗装が終わったら、細部のチェックと必要に応じて微修正(タッチアップ)を行います。
- チェックポイント:
- 塗りムラやダレ(たれ落ち)はないか
- 縁切り処理(瓦の重なり部の水抜き)がされているか
- 屋根以外に塗料が飛散していないか
- 施主立ち会い確認を行うケースも多く、不明点はこの段階で確認します。
- その後、足場を解体・清掃を行い、工事完了となります。
5-8 ステップ8:保証書の発行・アフターサポート
信頼できる業者であれば、施工完了後に「保証書(5〜10年)」が発行されます。また、1年後点検や定期メンテナンスの案内など、アフターフォローの体制が整っているかも、業者選定時の重要な判断基準です。
5-9 工期の目安(天候にもよる)
| 工程内容 | 所要日数(目安) |
| 足場組立+養生 | 1日 |
| 高圧洗浄+乾燥 | 1〜2日 |
| 補修+下地処理 | 1日(劣化状況による) |
| 下塗り〜上塗り | 2〜3日(乾燥込み) |
| チェック・足場解体・清掃 | 1日 |
| 合計(標準) | 5〜7日程度 |
| 天候不良を含めた想定 | 7〜10日程度 |
瓦屋根の塗装は、見えないところで多くの工程と丁寧な作業が必要です。特に高圧洗浄や下地処理、乾燥時間の管理が仕上がりと耐久性に大きく影響します。
工期は約1週間が目安ですが、天候によって前後するため、余裕を持ったスケジューリングが重要です。信頼できる業者を選び、事前に工程や日程をしっかり確認しておくことで、安心して塗装工事を任せられます。
6.塗料の選び方とおすすめの種類
瓦屋根の塗装に使用する塗料は、その種類によって耐久性・防水性・価格が大きく異なります。使用する塗料次第で、次回のメンテナンスまでの期間やコストパフォーマンスにも影響が出るため、目的や予算に応じた適切な選択が重要です。
6-1 塗料選びの基本的な考え方
塗料を選ぶ際は、以下のような観点から総合的に判断しましょう。
| 観点 | 内容のポイント |
| 耐久性 | 塗り替えまでの目安年数。10年以下か15年以上かで費用対効果が変わる |
| 防水・耐候性 | 紫外線・風雨・凍結への強さ。屋根は外壁よりも過酷な環境にさらされる |
| 美観 | ツヤあり/ツヤなし/マットなど。見た目や色持ちも重要 |
| 機能性 | 遮熱、防カビ、防藻、低汚染などの付加価値 |
| 価格 | 平米単価(㎡)の差と、総額でのバランス |
6-2 主な塗料の種類と特徴(瓦屋根対応)
| 塗料の種類 | 耐用年数の目安 | 特徴・メリット | ㎡単価の目安(施工費込み) |
| ウレタン | 約5~8年 | 安価で柔軟性があるが、耐候性はやや低め | 1,800~2,800円 |
| シリコン | 約8~12年 |
耐久・防水・価格のバランスが良く、最も採用されやすい |
2,000~3,000円 |
| フッ素 | 約12~15年 | 高耐候・高光沢・汚れに強い。価格はやや高め | 3,000~4,800円 |
| 無機塗料 | 約15~20年 | 紫外線や熱に強く、塗り替え頻度を最小限に抑えられる | 4,500~6,000円 |
| 遮熱塗料 | 上記に準ずる | 太陽熱を反射して屋根の温度上昇を抑える。機能性重視 | 上記+500~1,000円前後 |
※価格は瓦の状態・足場費・地域差によって変動します。
6-3 瓦屋根におすすめの塗料
モニエル瓦・セメント瓦に最適
- スラリー強化プライマー × シリコン・フッ素塗料の組み合わせ
下地が特殊なため、専用下塗り材を併用することで密着性を確保しつつ、耐久性の高い塗料を選ぶのがポイントです。
高温地域・日差しが強い立地
- 遮熱塗料(遮熱シリコン・遮熱フッ素など)
屋根表面の温度上昇を抑え、屋内の冷房効率を向上させたい場合に有効です。
メンテナンス回数を減らしたい場合
- 無機塗料・高耐久フッ素塗料
価格は高めですが、塗り替え周期が長く、長期的なコスト削減につながります。
7.DIYと業者依頼、どちらがいい?
瓦屋根の塗装は、結論から言えばDIYではなく専門業者に依頼することを強くおすすめします。理由は、施工の難易度、安全性、仕上がり品質、将来的なリスクを含め、個人が手を出すにはリスクが非常に高いためです。
7-1 DIYをおすすめしない理由
・高所作業の危険性が極めて高い
屋根の上は傾斜があり、転落事故のリスクがあります。命に関わる事故に発展するケースも珍しくありません。
…必要な知識・技術・道具が多く、準備が大変
高圧洗浄・下地処理・縁切り・塗料選定など、専門的な技術が必要です。不備があると数年で塗膜が剥がれ、雨漏りの原因になります。
・結果的に費用が高くつくことも
足場の設置、道具の購入、やり直しの材料費を含めると、業者に依頼した方が長期的に安く済む場合もあります。
・保証やアフターフォローが一切ない
不具合が起きても自己責任。対応に追われ、余計なストレスを抱えることになります。
7-2 業者に依頼するメリット
- 安全かつ効率的な施工
- 仕上がり品質が高く、長持ち
- 保証やアフターメンテナンス付きで安心
- 火災保険や補助金申請の対応も可能
プロの知識と技術で行う塗装は、建物の寿命や美観を確実に守ってくれます。
瓦屋根の塗装は、高い専門性と安全管理が求められる作業です。DIYに挑戦したい気持ちは理解できますが、失敗時のリスクや手間を考えると、専門業者に依頼するのが最も現実的かつ安全な選択です。
後悔しない屋根塗装のために、信頼できる業者を見つけ、しっかりと比較・相談することから始めましょう。
8.瓦屋根の塗装に関するよくある質問(Q&A)
屋根の塗装に関しては、検討中の方から多くの疑問や不安の声が寄せられます。ここでは、特に問い合わせが多い内容をQ&A形式でまとめました。
8-1 Q1. すべての瓦に塗装は必要ですか?
- 必要ありません。
粘土瓦(日本瓦・いぶし瓦・陶器瓦など)は、焼成によって表面がガラス質になっており、防水性が高く塗装の必要はありません。むしろ塗装すると剥がれやすく、逆効果になることもあります。塗装が必要なのは、主にセメント瓦・モニエル瓦・金属瓦です。
8-2 Q2. 屋根塗装のタイミングはいつが最適?
- 一般的には築10〜15年が目安です。
ただし、劣化症状(色あせ、ひび割れ、苔の繁殖など)が出ていれば、築年数に関係なく塗装を検討すべきです。特にセメント系瓦は、塗膜が防水機能を担っているため、早めの対応が重要です。
8-3 Q3. 雨漏りしてから塗装すればいいですか?
- 雨漏り前の予防が理想です。
塗装はあくまで“予防策”です。すでに雨漏りしている場合は、塗装ではなく補修や葺き替えが必要なこともあります。まずは点検を受けて、屋根の状態を正しく把握しましょう。
8-4 Q4. 火災保険や助成金は使えますか?
- 条件を満たせば利用可能な場合があります。
台風・落雪・地震などの被害による補修であれば、火災保険の対象になることがあります。また、一部自治体では省エネ塗装などに補助金を出しているケースもあるため、お住まいの地域の制度を調べておくとよいでしょう。
8-5 Q5. 業者選びで気をつけるべき点は?
- 施工実績・保証内容・説明の丁寧さを確認しましょう。
訪問営業や極端に安い業者には注意が必要です。信頼できる業者は、劣化状況を丁寧に説明し、見積もりも詳細です。また、アフター保証(5〜10年)なども含めて比較検討するのが安心です。
9.まとめ
瓦屋根の塗装は、見た目の美しさを取り戻すだけでなく、防水性・耐久性を高めて住まい全体の寿命を延ばす重要なメンテナンスです。しかし、瓦の種類によっては塗装が不要なものもあり、誤った判断は施工トラブルの原因にもなり得ます。
この記事では、以下のようなポイントを中心に解説しました。
- 塗装が必要な瓦と不要な瓦の違い
- 塗装の費用相場と内訳
- 劣化サインや適切なタイミングの見極め方
- 塗装の工程と工期、選ぶべき塗料の種類
- DIYのリスクと業者依頼の重要性
- 塗装に関するよくある疑問と対処法
これらをふまえたうえで、まずやるべきことは、自宅の屋根の状態を正確に把握することです。信頼できる業者に点検を依頼し、プロの診断を受けたうえで、塗装・補修・葺き替えなど最適な対策を検討しましょう。
定期的なメンテナンスを適切なタイミングで行うことで、大切な住まいを長く安全・快適に保つことができます。屋根塗装は“家を守る投資”として、ぜひ前向きに検討してみてください。