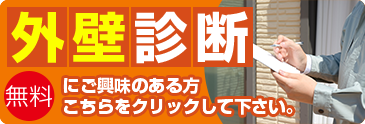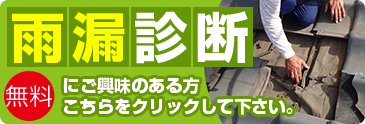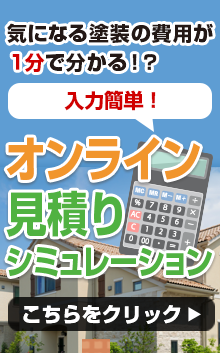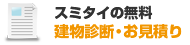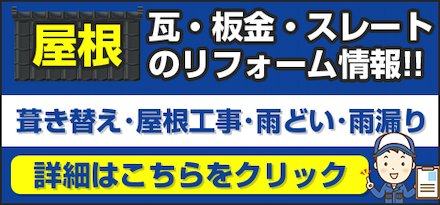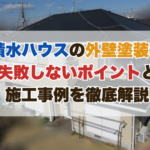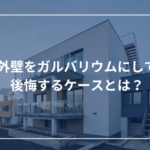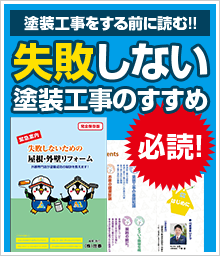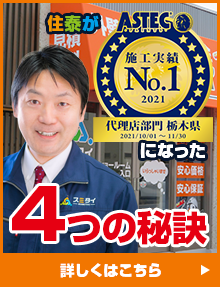屋根の色褪せ・サビは劣化のサイン!放置するとどうなる?症状と対策を解説
2025.09.18 (Thu) 更新

屋根は普段なかなか目にする機会が少ない場所ですが、住まいを守る最前線として常に紫外線や雨風にさらされています。そのため、年月とともに「色褪せ」や「サビ」といった劣化の症状が出てきます。
「少しくらい色が薄くなっただけ」「まだ雨漏りはしていないから大丈夫」そう思って放置してしまう方も少なくありません。
しかし実際には、色褪せやサビは屋根が発している劣化のサインであり、放置すれば雨漏りや屋根の葺き替え工事など大がかりな修繕につながる恐れがあります。
本記事では、屋根の色褪せやサビの診断ポイント、放置した場合のリスク、そして適切なメンテナンス方法について詳しく解説します。
目次
屋根の色褪せとは?
屋根の色褪せとは、表面の塗膜が劣化して防水性や美観を失っている状態のことです。新築直後は艶やかな色合いを保っていますが、5〜10年ほど経過すると少しずつ色が薄くなり、白っぽく見えるようになります。

色褪せの主な原因
-
紫外線の影響
屋根は建物の中で最も日差しを受けやすい部分です。紫外線は塗膜を分解し、色素を劣化させていきます。 -
雨風による摩耗
風に乗って運ばれる砂やほこり、雨水が繰り返し当たることで表面が削られていきます。 -
排気ガスや汚れの付着
車の排気ガスや工場の煙などの大気汚染物質が付着することでも、変色や色褪せが進行します。 - 経年による塗料の耐久性低下 屋根に塗られている塗料は、ただ色をつけているだけではなく 防水性や防錆性を担う保護膜 の役割をしています。
しかし、どんな塗料でも 経年劣化 により性能は少しずつ低下していきます。
色褪せの診断チェック

-
屋根全体の艶がなく、白っぽく見える
-
部分的に色が薄くなり、ムラが出ている
-
外壁と比べて屋根の色が極端にくすんでいる
👉 ポイント
色褪せは一見すると「見た目の問題」と思われがちですが、実際には塗膜の防水機能が失われているサインです。この段階で放置すると、次のサビや劣化へとつながっていきます。
屋根のサビとは?

特にトタン屋根やガルバリウム鋼板屋根といった金属屋根に起こりやすいのが「サビ」です。サビは金属が水や酸素と反応して腐食する現象で、一度発生すると徐々に広がっていきます。
サビの種類と進行段階
-
点サビ
小さな斑点状のサビ。早めに見つければ研磨と防錆塗装で対応可能。 -
広範囲の赤サビ
屋根全体が赤茶色に変色している状態。進行すると屋根材がもろくなってきます。 -
穴あきサビ
腐食が内部まで進み、屋根材に穴が開いてしまう状態。この段階では塗装では対応できず、葺き替えやカバー工法が必要になります。
サビが発生しやすい箇所

-
トタン屋根やガルバリウム鋼板の表面
-
釘やビスなどの金属部分
-
谷板金・棟板金のつなぎ目
サビの診断チェック
-
屋根表面に赤茶色や黒っぽい斑点が見える
-
雨樋や外壁にサビ水が流れ落ちて筋状の跡がある
-
屋根材の一部がめくれている、穴が見える
👉 ポイント
サビは一度発生すると進行が早いため、「点サビ」の段階で見つけてメンテナンスすることが重要です。
屋根の色褪せやサビを放置するとどうなる?
屋根の色褪せやサビをそのままにすると、次のようなリスクが発生します。
-
防水性の低下
塗膜の役割がなくなり、雨水を吸収しやすくなる。 -
サビの進行による穴あき
金属部分に穴があき、雨漏りの直接的な原因に。 -
屋根材の破損・飛散
劣化した屋根材は強風で割れたり剥がれたりしやすくなる。 -
雨漏り・室内への被害
天井や壁のシミ、カビ、構造材の腐食につながる。 -
修繕費用の高額化
軽微な塗装で済むはずが、放置すると葺き替えや大規模工事が必要になる場合も。
色褪せ・サビの対策方法
劣化を発見した際には、早めの対応が大切です。
1. 定期点検
10年に一度を目安に、専門業者による屋根点検を行いましょう。自分で屋根に上るのは危険なので、プロに依頼するのがおすすめです。
2. 屋根塗装
色褪せや軽度のサビなら塗装で防水性・美観を回復できる。遮熱塗料を選べば省エネ効果も。
3. 部分補修
棟板金の釘浮きや軽度のサビは、部分的な補修で対応可能。
4. 葺き替え・カバー工法
劣化が著しい場合は、屋根を新しくする工事を検討する。長期的な安心につながる。
まとめ
屋根の色褪せやサビは、単なる見た目の問題ではなく「劣化のサイン」です。放置すれば雨漏りや建物全体の寿命に関わる重大なトラブルへ発展することもあります。
「少し色が薄いだけだから…」と思わず、早めの点検・メンテナンスを心がけましょう。